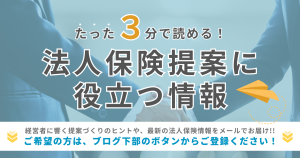役員借入金についての理解を深める(後半)ーたった3分で読める【法人保険提案】HELLO通信
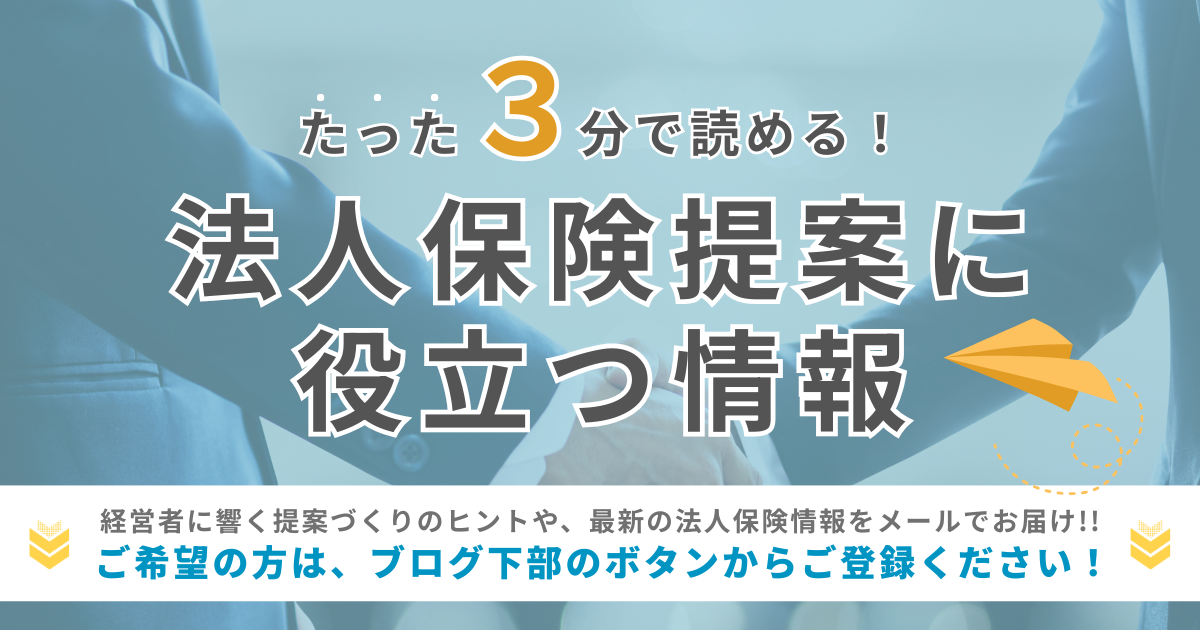
前回は、「役員借入金」と「役員借入金への影響」について解説しました。
今回は続きを説明していきます。
▶返済スキームで手取りを高め、役員借入金を減らす
役員借入金残高を早期に減らす手段として「役員報酬の一部を返済に振替える」方法が有効です。
たとえば現行報酬一千万円から八百万円に減額し、差額二百万円を元本返済に充当すると、個人側は所得税・住民税・社会保険料が軽減され、返済金は非課税で受領できるため可処分所得が増える場合があります。
ただし法人側では損金が減るため法人税負担が上昇する点を必ず試算しましょう。
▶役員借入金に利息を適用することができる
「役員借入金」の利息を受け取る社長はごく少数です。
税法上、社長が会社から正当な利息を受け取ることはまったくの合法であり、むしろ会社にも社長にも大きなメリットをもたらします。
利息を支払った会社側は、その金額を営業外費用として損金算入できるため法人税が圧縮される一方で、受け取る社長側は利息を雑所得として申告します。
この点がポイントで、雑所得は給与所得と異なり社会保険料の算定基礎に含まれないので、たとえば役員報酬を減額し、その分を利息として受け取る設計に組み替えると、
会社:人件費を削りつつ利息で損金を確保し、負担はほぼ横ばい
社長:給与が減るため社会保険料と所得税がダウン。利息には保険料がかからず、手取り額が増える
となり、同じキャッシュフローでも、“報酬”より“利息”に名目を変えるだけで双方が得をするわけです。
ただし利息を計算する際に、市場金利を大幅に上回れば「過大支払」として損金否認・役員賞与認定のリスクが生じるので、あくまで金融機関から融資を受ける際の金利程度にしておくことが望ましいとされます。
ちなみに会社が社長にお金を貸す場合、無利息や低利率だと「みなし給与」として社長に課税され、会社は受取利息の計上漏れで追徴を受ける可能性がある。
借入金とは逆に、“利息を付けることが前提”である点を忘れないようにしましょう。
次回は『一括払い保険が企業財務に与える影響~二つの指標で読み解く経営防衛~』について2回に分けて解説していきます。
楽しみにしていてください!
メールマガジンでは最新の投稿をお届けしています。法人保険の営業・ご提案にお役立てください。