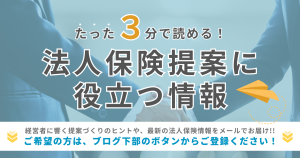連帯保証債務の「見えない相続リスク」—保険募集人が押さえるべき連帯保証債務の知識(前半)ーたった3分で読める【法人保険提案】HELLO通信
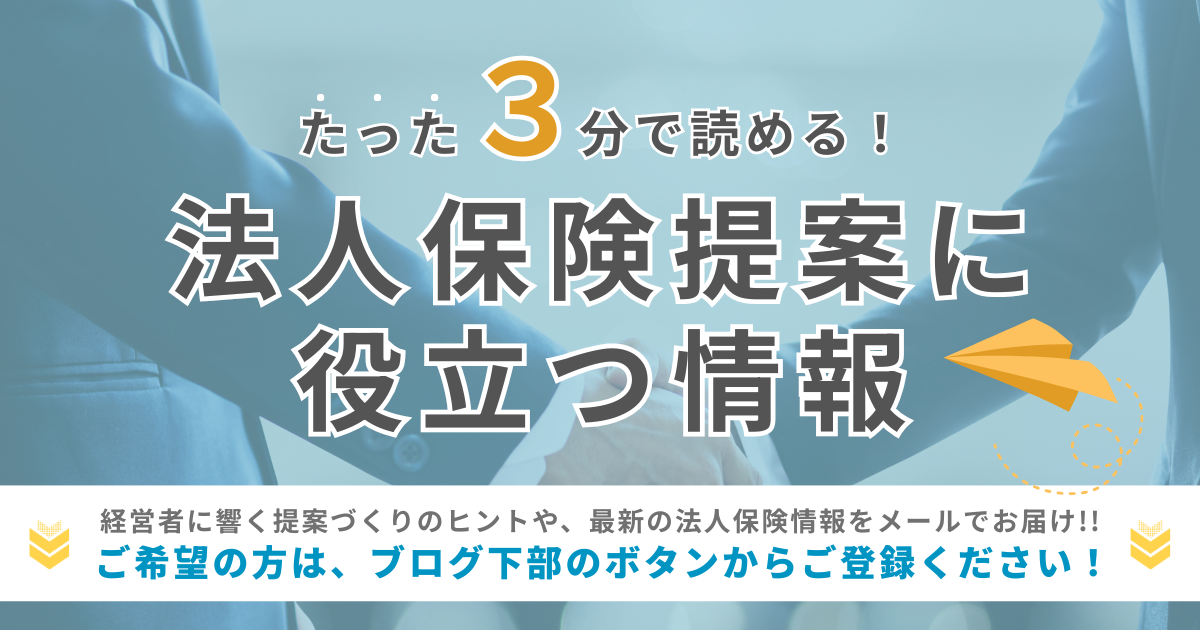
「社長が倒れた後、家族に届く通知が『残高一括請求』だったら——」。
そう問い掛けると、多くの経営者が一瞬黙り込みます。
連帯保証債務は見えない債務であり、家族が把握できていない可能性も十分あるのです。
法人保険で最も提案する機会が多いであろう「事業保障対策」において、「連帯保証債務」は大きなテーマとなります。
金額も大きくなることが多いですし、後継者にとって連帯保証債務の問題は家族も巻き込む話になりますので、慎重に取り扱う必要があります。
▼連帯保証債務は主債務者と同一の責任である
中小企業経営者の7割超が借入契約で自ら連帯保証人になっています。
連帯保証は主債務者と同一の責任を負うため、金融機関は本人の資産売却や競売を待たず、保証人の自宅・預金・保険解約返戻金にいきなり仮差押えをされる可能性もあります。
▼催告・検索の抗弁権がない怖さ
そもそも保証人が最後の防波堤として行使できるのが「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」といわれる権利です。
催告の抗弁権とは、債権者に対し「まず主たる債務者に請求してほしい」と猶予を求める権利であり、たとえば飲食店オーナーが返済を滞らせた際、友人の通常保証人はこの権利を行使して督促を一時的に回避できます。
つまり銀行はオーナー本人への請求と差し押さえを先に試みる事となります。
一方の検索の抗弁権は「主債務者に強制執行可能な財産が残っているなら、そちらから換価して不足分だけ請求してほしい」と主張できる防衛策です。
例えばA社が返済を延滞している状況において、A社の工場に抵当権未設定の機械設備が残っている場合、保証人は銀行にその競売を優先させるよう求める事ができます。
機械売却で補填できる分だけ債務が減るため、保証人の自宅や預金を守れる可能性があるという事です。
ところが連帯保証契約では、この二つの抗弁権が契約で放棄されます。
債権者は主債務者の財産処分を待たずに保証人へ即座に全額を請求できるため、飲食店オーナーが再建途中でも保証人の口座は差し押さえられ、機械設備が残っていても工場より先に保証人の自宅が競売に掛けられる。
これが「連帯保証債務」の怖さです。
次回は『連帯保証債務の「見えない相続リスク」—保険募集人が押さえるべき連帯保証債務の知識(後半)』にて、「連帯保障債務」「経営者保証に関するガイドライン」「連帯保証債務リスクに生命保険で備えること」についてお届けします!
楽しみにしていてください!
メールマガジンでは最新の投稿をお届けしています。法人保険の営業・ご提案にお役立てください。