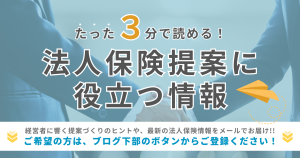2026年は「保障回帰元年」~3つの視点から考える~(後半)ーたった3分で読める【法人保険提案】HELLO通信
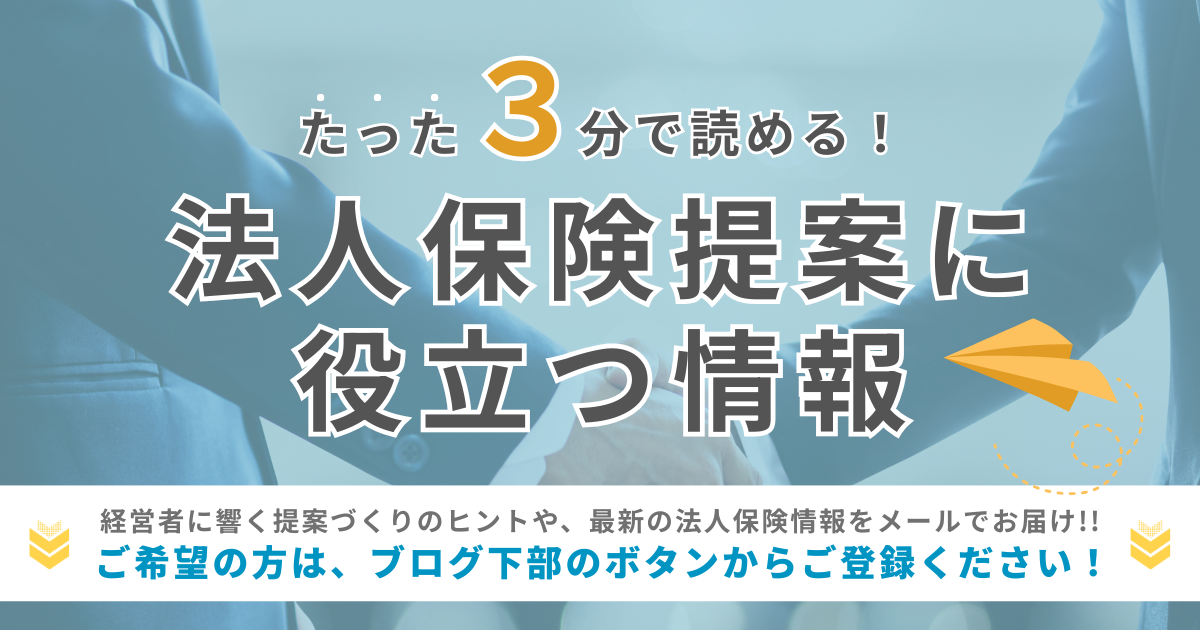
前回は、「2026年の保険業界」はどうなっていくのか・そしてどのように立ち振る舞うべきなのかについて【3つの視点】の1つ目について、解説しました。
今回は、「リスクマネジメントの基本的な対応策」と残り2つの視点と「3つの視点全てに共通するキーワード」についてお伝えしたいと思います。
▶2つ目の視点~金融機関がBCPを重視するようになった~
BCP(事業継続計画)とは、大災害・感染症・サイバー攻撃など不測の事態でも会社を止めないための行動マニュアルです。
その中には「経営者不在シナリオ」も含まれ、代表者が事故や死亡で意思決定不能になった瞬間、誰が権限を継承し、資金決済や顧客対応を行うのか、社内外の連絡網をどう維持するのか――これらを事前に明文化することで混乱を最小化できます。
こうした準備を済ませた企業に対し、銀行はリスクを正確に測れるとして金利を通常融資より引き下げる優遇融資を導入するところも増えており、信用保証協会ではBCP策定が出来ている企業専用の融資制度も存在します。
BCPは任意の取り組みではなく、資金調達コストと企業評価を左右する“第二の決算書”になりつつあり、未整備の中小企業は着手すべき段階に入りつつあります。
▶3つ目の視点~引き続き全損保険のピーク対応が求められる~
先述した通り、長期平準定期の返戻率ピークは2025年以降に集中し、解約は既に立て続けに起こっています。
解約と同時に死亡保障が消滅し、社長に万一が起これば借入返済・運転資金・納税資金が一挙に不足します。
ピーク後の“保障空白”は企業存続を脅かす最大の死角ですので、必要なのは返戻金の原資に保障型商品へ振り向け、必要保障額を試算し直す提案です。
3つの視点全てに共通するキーワードは「保障」です。
中小企業経営者にとって「保障が絶対に必要である」とは言えませんが、少なくとも「保障が必要かどうかを考える」必要はあります。
それは中小企業経営者が「株主としての責任」・「経営者としての責任」「家族を支える個人」としての責任、この3つの責任を抱えており(もちろん全ての中小企業経営者が抱えているわけではありません)、万一の場合に多方面に影響を与える可能性が高い為です。
本来の目的である「保障」が重要なのは当然の事、時代の流れからも保障提案の精度を高めていく事が保険募集人の方にとって、今後極めて重要な戦略です。
今一度、生命保険の本質と向き合ってみてはいかがでしょうか。
次回は『連帯保証債務の「見えない相続リスク」—保険募集人が押さえるべき連帯保証債務の知識(前半)』にて、『連帯保証債務の怖さ』についてお届けします。
楽しみにしていてください!
メールマガジンでは最新の投稿をお届けしています。法人保険の営業・ご提案にお役立てください。