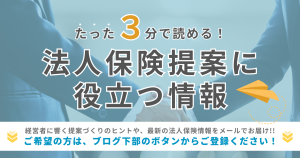役員借入金についての理解を深める(前半)ーたった3分で読める【法人保険提案】HELLO通信
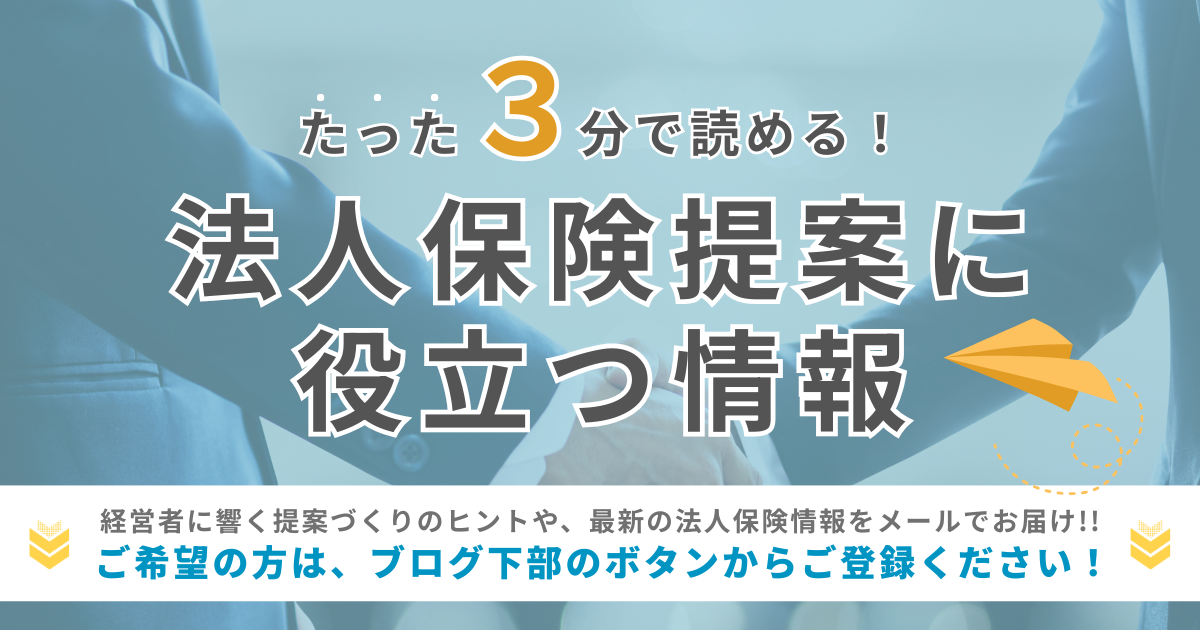
保険募集人として経営者を支援する際に「役員借入金」は見落とせないテーマです。
適切に整理できればキャッシュフロー改善、金融機関評価向上、相続対策まで一気通貫で解決できますので、顧客への貢献は相当大きいものとなります。
本記事では「役員借入金」に関して保険募集人の方が知っておくべき事をお伝えしていきます。
▶役員借入金とは?
役員借入金は、社長など役員が会社に貸し付けたお金の事です。
迅速に資金注入できる一方、返済条件や利率が曖昧なまま残高が膨らみやすい事もあります。
また、役員借入金は社長の債権=社長個人の資産であり、相続時には相続財産として計上されますが、相続人が「父が会社に貸していた資金を返済してください」と請求してきた場合、会社の資金繰りが逼迫していれば即時返済できず経営危機に発展しかねないというリスクがあります。
また、役員借入金が現役社長本人からの貸付であれば金融機関は「実質自己資本」とみなします。
しかし役員借入金相続により、「事業に関与しない妻や子ども」へ債権が移った途端に金融機関の帳簿上で役員借入金は負債へ組み替えられることも注意が必要です。
また、そもそも役員借入金の金額が多額である場合、相続税の納税資金を準備しなければならない状況に陥ります。
この納税資金については生命保険を活用して準備することがよくありますね。
▶役員借入金が経営者保証に影響する?
「経営者保証」については、経営者による思い切った事業展開や事業再生、事業承継を妨げる要因になっており、これらの課題の解決策として、全国銀行協会と日本商工会議所が「経営者保証に関するガイドライン」を策定した経緯があります。
このガイドラインは「中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルール」という位置づけである為、法的な拘束力はなく、経営者保証を解除するかどうかの最終的な判断は、金融機関にゆだねられます。
ガイドラインに法的な拘束力はないものの、実際に金融機関で勤務経験がある私の意見としては、基本的にこのガイドラインが経営者保証を外すかどうかの主要の判断材料になっていました。
具体的には
1)資産の所有やお金のやりとりに関して、法人と経営者が明確に区分・分離されている
2)財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能である
3)金融機関に対し、適時適切に財務情報が開示されている
の3要件を将来に亘って充足する体制が整備されていることが経営者保証を外すかどうかの判断材料とされています。
「役員借入金が存在すること」は3要件の1に該当する為、役員借入金を完済することは「経営者保証」という観点でも望ましい事です。
次回は「役員借入金についての理解を深める(後半)」にて、「返済スキームで手取りを高め、役員借入金を減らすこと」と「役員借入金に利息を適用することができること」についてお届けします。
楽しみにしていてください!
メールマガジンでは最新の投稿をお届けしています。法人保険の営業・ご提案にお役立てください。