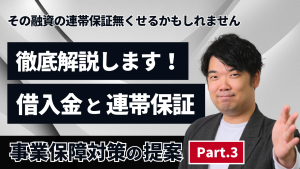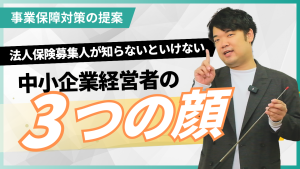中小企業経営者に向けた事業保障対策2|社長に万が一が起きた時の備えを考える
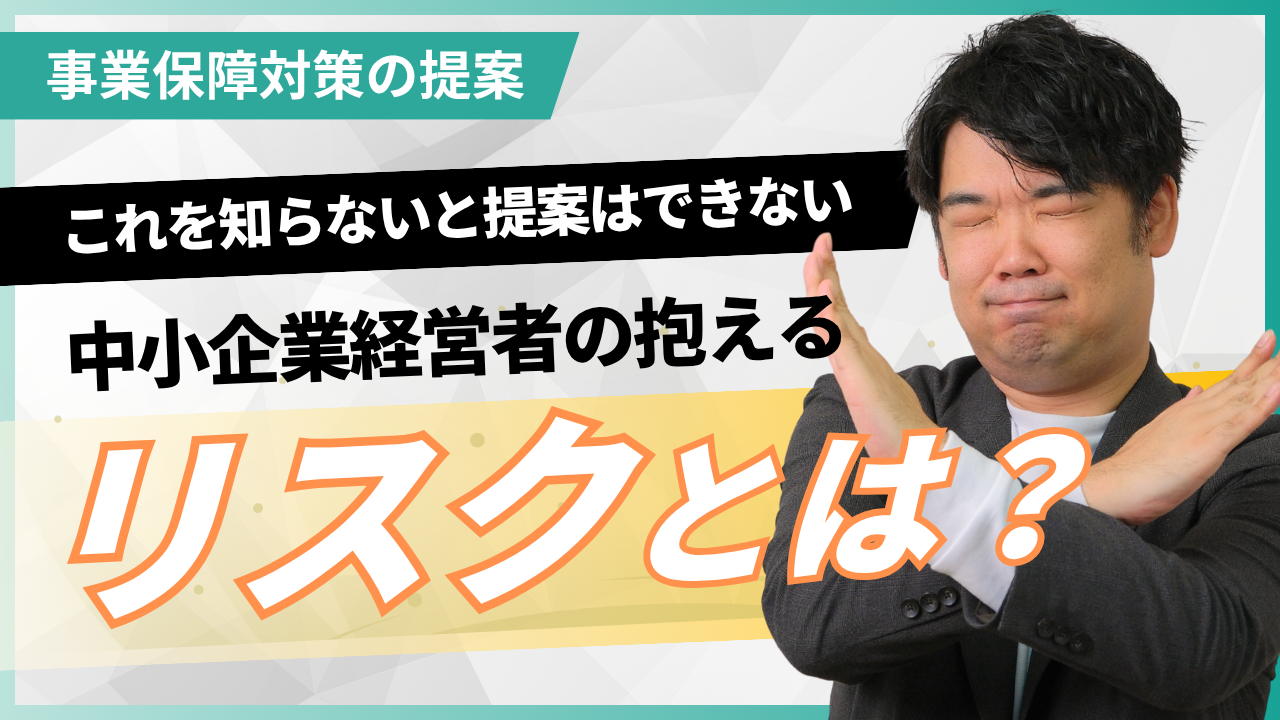
事業保障対策とは?社長に万が一が起きた時の備えを考える
こんにちは。ハローベースの渡邉です。
今回は、経営者に向けた「事業保障対策」についてお話しします。
前回は、生命保険のニード喚起について解説しました。今回は、そのニードを感じてくださった社長に対して、具体的にどのような話をしていけばよいのか、そのポイントをお伝えします。
まずは「会社の方向性」を確認することから
事業保障対策の出発点は、社長に万が一のことがあった場合、会社はどうなるのかを把握することです。
突然ですが、今、皆さんの身近にいる社長さんをひとり思い浮かべてみてください。
その方に万が一のことがあったとき、その会社はどうなりますか?
会社の進む道は大きく分けて2つです。
①会社を継続する(=後継者がいる)
②会社を清算する(=後継者がいない)
このどちらを選ぶのかによって、会社が抱えるリスクや必要な対策はまったく異なります。
これを把握していない状態では、適切な保険提案を行うことはできません。
【継続】後継者がいる場合に発生する4つのリスク
会社を継続する場合、まずは「誰が後を継ぐのか」を確認します。
親族か、あるいは親族外かによって、特に連帯保証のリスクが変わってきます。
継続の際に出てくる代表的なリスクは以下の4つです。
①借入金・連帯保証の問題
親族外の後継者にとっては、前経営者の連帯保証を引き継ぐことに大きな不安があります。
②株式の承継問題
社長が保有していた株式は相続対象になります。
後継者が株式を持たないと、会社運営に支障をきたす可能性があります。
③業績不安
特に創業社長が亡くなった場合、会社の信用や売上に大きな影響が出ることがあります。
④ご遺族の生活資金
社長は家族の大黒柱であることが多く、遺族の生活保障も大きなテーマになります。
【清算】会社をたたむ場合に必要な対策
後継者がいない場合は、会社を清算することになります。こちらにも大きなリスクがあります。
①借入金の返済資金
会社を清算するには、すべての債務を返済する必要があります。
②遺族の生活資金
継続と同じく、ご遺族に対する保障は重要です。
③従業員の転職支援資金
突然の閉鎖で仕事を失う従業員の支援も、経営者としての責任のひとつです。
④清算までの運転資金
会社はすぐには閉じられません。清算には通常6ヶ月〜1年かかるため、その間の運転資金が必要です。
継続か清算かで、必要な資金もリスクも変わる
よく「借入金と運転資金6ヶ月分を準備していればOK」といった話を聞きますが、それは一部の話でしかありません。
継続か清算か、それぞれで必要な準備資金は違います。以下のように分類できます。
◆ 継続の場合に必要な資金
・借入金返済資金(連帯保証リスク対応)
・死亡退職金(遺族の生活支援)
・自社株買い取り資金(株式の集中)
・業績悪化の補填資金(信用・売上対策)
◆ 清算の場合に必要な資金
・借入金返済資金
・死亡退職金
・従業員の転職支援資金
・清算完了までの運転資金
まとめ|社長に万が一が起きたら、まず考えるべきこと
改めてお伝えします。
事業保障対策を考える上で最も大切なのは、
「会社は継続するのか、それとも清算するのか」を明確にすることです。
そして、選択肢によって発生するリスクも、準備すべき資金も異なります。
この違いをしっかり整理したうえで、社長にとって本当に必要な保障内容を提案していくことが、信頼される保険募集人としての第一歩です。
今回の内容も、YouTube動画でも詳しく解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
ながら聴きでも繰り返し“聞く”ことで理解が深まります。ぜひ作業中や移動中にもご活用ください。
【事業保障対策の提案②】ニード喚起後にどう話す?会社の方向性に応じた対策提案