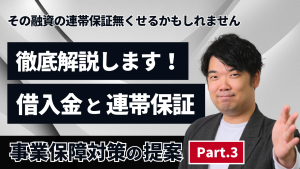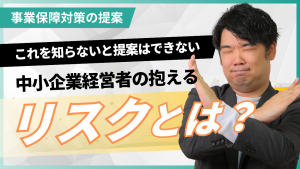中小企業経営者に向けた事業保障対策|三つの顔でニード喚起する方法
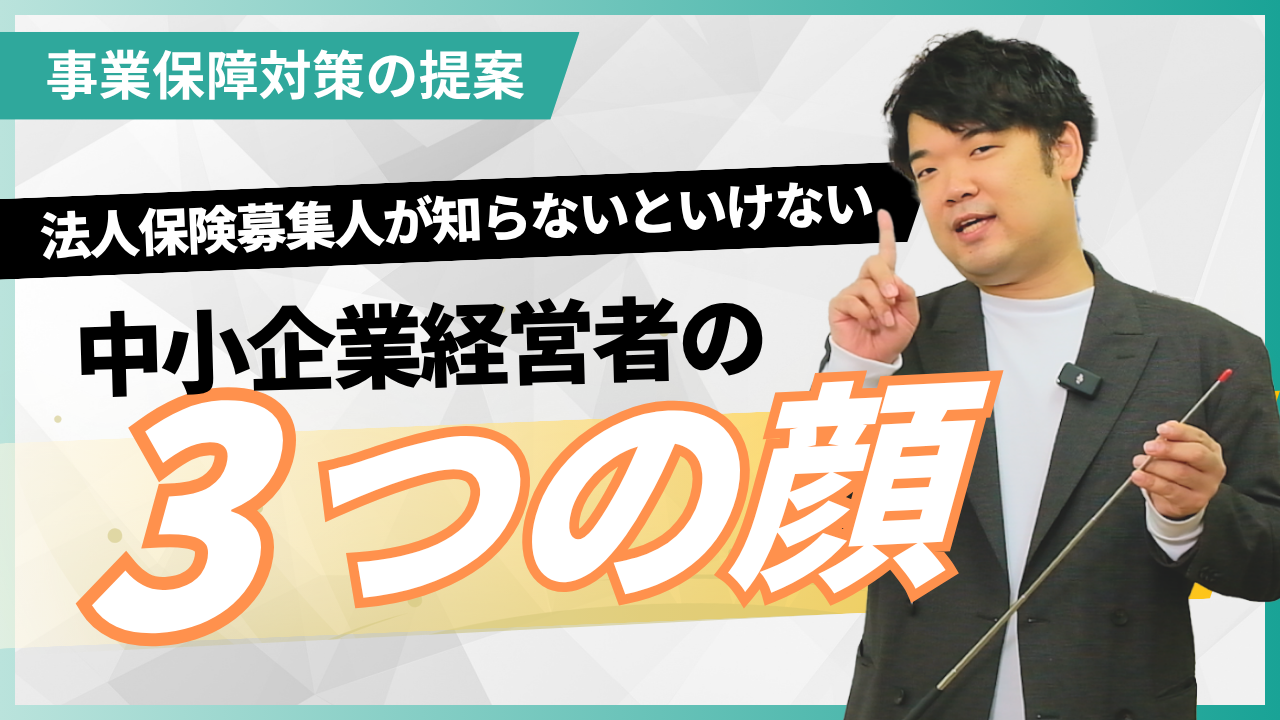
【中小企業経営者に向けた事業保障対策】「三つの顔」でニード喚起する方法
こんにちは。ハローベースの渡邉です。
今回は「事業保障対策の提案」における第一歩、「どのようにニード喚起するか」についてお話します。
このブログ記事は、保険募集人の方が法人保険を提案する際に必ず押さえておきたい基本の考え方を整理した内容です。YouTube動画『【事業保障対策の提案①】経営者が気づいていないリスクをどう伝える?』でもわかりやすく解説しています。
ぜひあわせてご視聴ください。
なぜ「ニード喚起」が重要なのか?
まず法人保険を提案するうえで最初に必要なのは、「事業保障対策の必要性」を経営者に理解してもらうことです。生命保険という商品は緊急性が低く、放置されがちです。
そのため、提案の前に「必要性に気づいてもらう=ニード喚起」が極めて重要になります。
その入口となるキーワードが「所有と経営の一致/分離」です。
所有と経営の一致、分離とは?
中小企業の多くは「所有と経営の一致」、つまり株主(所有者)と経営者が同一人物であることがほとんどです。
たとえば、会社の代表者が自ら株式を所有しているパターンがあります。
一方で、まれに親が株式を保有し、子が経営するような「所有と経営の分離」ケースもありますが、これは少数派です。
この「所有と経営の一致」が、中小企業の事業保障対策を考える際の前提となります。
中小企業経営者が持つ「三つの顔」
ニード喚起の具体的なポイントは、中小企業経営者が持つ「三つの顔」にあります。
①株主としての顔
株主は単にお金を出す人ではありません。50%超(以上ではありません)の株式を持っていれば、他の役員を解任できる権限があります。
権限があるということは、同時に「責任」もあるということです。
②経営者としての顔
従業員を守る責任があり、お客様に価値を提供し、社会的責任も背負っています。
日々の経営判断に加えて、事業の継続性にも大きな責任を持っています。
③家族の長としての顔
多くの経営者は一家の大黒柱でもあります。
万が一のとき、残された家族の生活をどう守るかという視点も欠かせません。
この三つの顔を認識したときに、「経営者が万一のことになった場合、会社・社員・家族それぞれに大きな影響を与える」ことが具体的に想像できるようになります。
なぜ、保険募集人のあなたが必要なのか
AIが進化する中、保険商品の比較や選定はAIでも可能になりつつあり、現在もすでに業界に進出してきています。
しかし、AIには「潜在的なニーズを引き出す力」はありません。
「なぜ、いまこの保障が必要なのか」を経営者に気づいてもらう、このニード喚起こそ、保険募集人にしかできない仕事です。
今回の内容は、YouTube動画でも詳しく解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
ながら聴きでも繰り返し“聞く”ことで理解が深まります。ぜひ作業中や移動中にもご活用ください。
【事業保障対策の提案①】経営者が気づいていないリスクをどう伝える?