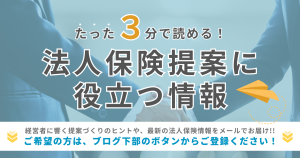一括払い保険が企業財務に与える影響~二つの指標で読み解く経営防衛~(後編)ーたった3分で読める【法人保険提案】HELLO通信
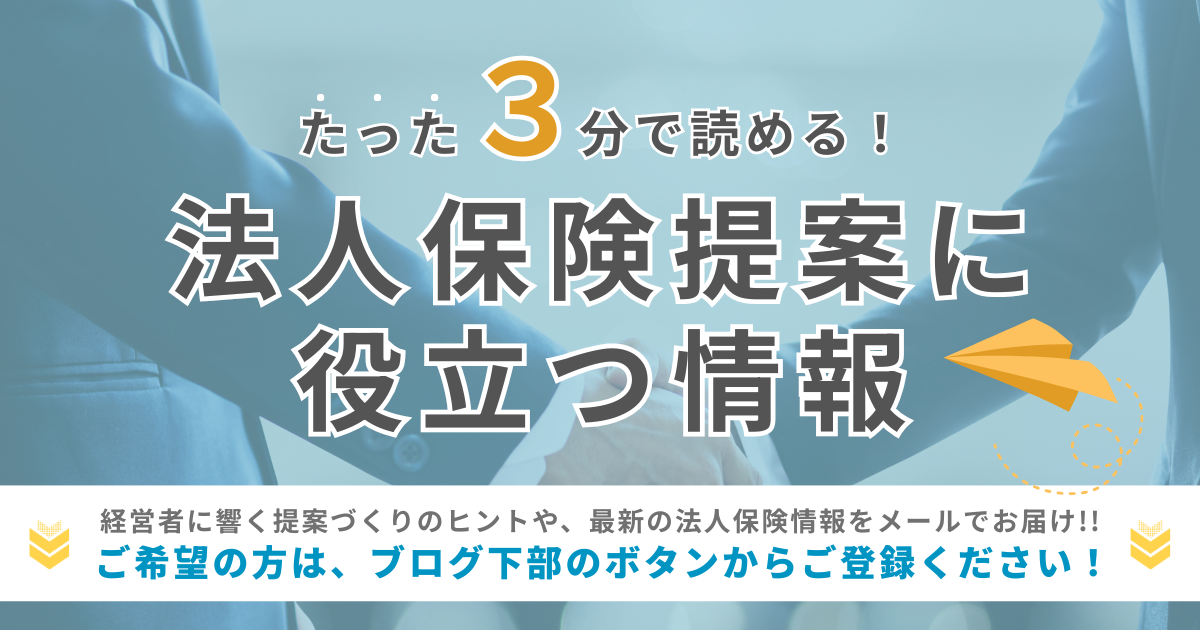
前回は、「一時払い保険をお預かりした時のBSの変化」と「流動比率」について解説しました。
今回は続きを説明していきます。
▶現預金販管費比率──“売上ゼロ”に耐える月数
現預金販管費比率は〈現預金÷月間販売費及び一般管理費×100〉で求められ、手元資金だけで何か月会社を維持できるかを測る指標です。
300%(3か月分)以上で安全圏、理想は600%(6か月分)とされ、一時払い保険料はこの比率にも大きな影響を与えます。
たとえば月間の販売管理費(固定費+変動販管費)が600万円、支払前の現預金が4,000万円の会社が、3,000万円を一括で保険料として支払うケースを考えてみましょう。
支払前の現預金販管費比率は 4,000万円÷600万円=約6.7か月。
つまり売上がゼロになっても半年強は会社を維持できる計算ということです。
しかし保険料を支払うと現預金は1,000万円に激減し、1,000万円÷600万円=約1.7か月へと急落。
わずか1か月半ほどで手元資金が尽きる水準に変わってしまいます。
流動比率だけでは現預金水準がわからないため、保険料算出の際はこちらの指標も確認する必要があります。
▶2つの指標から保険料の上限を設定する
流動資産が12,000万円、流動負債が5,000万円、現預金が4,500万円、月間販売管理費900万円の会社に対して「保険料の上限はどうなるのか」を見ていきましょう。
流動資産1億2000万円から保険料Pを差し引き、その残高を流動負債5000万円で割った値が200%を割り込まないようにするには、Pを「2000万円以下」に抑える必要があります。
次に現預金販管費比率ですが、現預金4500万円からPを引き、月間販売管理費を900万円で割った値が3か月分を下回らないようにするには、Pを「1800万円以下」に留めなければなりません。
2つの条件を同時に満たす最も小さい数字が保険料の上限にあるので、一括払いで拠出できる保険料の上限は1800万円となります。
支払い後でも流動比率は約204%、現預金販管費比率は3.0か月を維持でき、資金繰りへの影響も最小限に抑えられます。
前編と後編の2回にわたり、2つの指標から一時払いの保険商品を提案する際の保険料上限についてお伝えしました。
保険募集人である前に「金融人」であることを理解し、責任を持った保険提案をおこなっていきましょう。
次回は『法人保険提案は「企業理解」から始まる』について2回に分けて解説していきます。
楽しみにしていてください!
メールマガジンでは最新の投稿をお届けしています。法人保険の営業・ご提案にお役立てください。